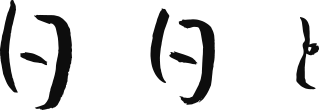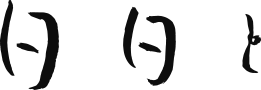最近の出来事
亜紀(A): お久しぶりです、志水さん。しばらくコラムをお休みしていましたね。
志水(S): そうですね、亜紀さん。
私は京都での設計業務に追われていました。店舗の内装設計や、お屋敷の設計や町家リノベーションのプロジェクトが2つ、重なってしまって。
A:重なると、大変ですよね。
私もここ数ヶ月、弊社の鎌倉のアトリエの一部を使って、長年温めていたプロジェクトを始動させていました。
なかなかコラムの時間が取れず。
S: それは興味深いですね。どんなプロジェクトなのですか?
A: 私は学生時代は美術史を学んでいて、以前は博物館や美術館のディスプレイやインテリアを手がける会社に勤めていたんです。
しばらくブランクがあって住宅の仕事に戻ってきたときに、改めて気づいたことがあって…
S: それは?
A: 日本のすまいに、なんかアートが無いんだよなあ、という現実です。
高いお金を出して名作家具は買うけれど、アートを買う人は少ない。
S:確かに、そうですね。
A:なぜだろうと考えていて、多くの人にとって、作家が身近な存在ではないからでは?と考えるに至りました。
作家さん自らに作品を説明してもらう、その作品への想いや制作過程を聞くことはとても重要な体験で、それによって、なぜその作品に惹かれたのかをきちんと言語化できるのだと思います。
作家と作品、それを鑑賞する自分自身にじっくり向き合う場所、美術館でも、ギャラリーでもない、アートへの接点を作りたいなと。
S: なるほど。それで亜紀さんが「場を開く」活動を始められたわけですね。
A: はい。そのための試みとして、会社のアトリエをアートに開く場「THEO」を始めました。
私の想いは、お客様が作家と直接話をして、気に入った作品を家に飾っていただくこと。
そうすることで、すまいはより自分たちらしく育っていく場になると思うんです。
S: 亜紀さん、思いついたら直感で行動しますからね、笑。どんな感じで進んでいますか?
A: 思ったより大変ですけど、ぼちぼち、動いてます。
年明けから、ふたりの方の展覧会を開催しました。写真や映像などコンセプチュアルな作品を発表している作家と、コマーシャル写真から、ファインアートに移行中の作家の写真展。
特に印象的だったのは、空間が作品に与える影響で、鑑賞者の動きや滞在時間まで変わるということでした。
何人かの方に「この空気感がいい」と言っていただいて、空間が持つ力を改めて実感しました。

S: 気づきですね。私たちが設計するすまいも、くらす人の感性や創造性に影響を与え続ける存在なんですね。
A: ええ。数値化できる性能も大切ですが、空間が持つ「気配」や「余韻」といった感覚的な質も同じくらい重要だと思います。
志水さんは最近のお仕事から考えることはありますか?
S: そうですね…実はクライアントワーク以外に、以前から考えていた自邸設計のアイディアを形に落とし込み始めました。
いざ自分で自邸を作るとなると、本当に色々考えます。価格のこと、性能のこと、デザインのこと。
A: いよいよ、自邸計画ですね!クライアントワークとどんな違いがありましたか?
S: 最大の違いは「将来の変化への余白を最大限残す」という考え方でしょうか。クライアントワークでは、求められることもあり、細部までデザインしがちなのですが、自分の家となると「この部分は今決めなくてもいいかな」と思えるんです。
A: デザインに「余白」を残すということですね。
S: そうなんです。例えば壁の仕上げ一つとっても、あえてシンプルにしておくことで、将来自分で手を入れる楽しみが残るんです。数年後に気分が変わったら塗り替えたり、気に入ったアートに出会えたら作品を飾ったりできるようにしておく。
空間も作り込みすぎなければ、自分以外のインテリアデザイナーに、一部の内装をお願いして新しい見え方を楽しむこともできる。
A: 最近の高性能住宅と言われる注文住宅は、とても丁寧にデザインされているので、住む人の「手を入れる余地」が少ないように感じることがあります。お施主さんも、設計者に言われたように、真面目に住んでいる感じ。
S: 完璧にデザインされた空間は確かに美しいのですが、暮らしってもうちょっとラフなものかな、と。
それに、もし将来売却することになったとしても、おおらかなデザインであれば、次に住む方が自分の色に染めやすいんです。細部までデザインし尽くさないことで、設計や施工の価格も抑えられる。
A: 住む人が参加できる余地を残した家づくりということですね。設計者としては言いにくい部分でもあるかとは思いますが。
S: そうですね、だから自邸でチャレンジしてみます。それが良ければ納得されるお客様もいるでしょうし。
もちろん、機能性やデザイン性を犠牲にするわけではなく、基本性能はしっかり確保した上で、住む人が時間をかけて育てていける大らかさを大事にする。
「完成された家」ではなく「育つ家」を提案するという感じでしょうか。
結局、家はくらすためのもの。
インスタ映えする写真のためではなく、実際に住む人が愛着を持って長く大切にできる空間であってほしい。
そのためには、少し「手を抜く」勇気も必要かもしれませんね。
A: 「手を抜く勇気」…住宅設計で一番難しいのって、やりすぎないことなのかもなあ。
S: そうなのかもですね。
亜紀さんがアトリエでの経験を通して感じた「空間が人に与える影響」、僕の伝えたい「おおらかな家」の考え方。そんな考え方を持ち寄って、次のいい仕事がしたいですね。