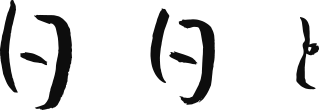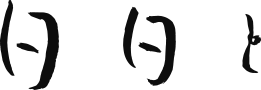自由学園が育んだ学園都市の風景
ライトを継承する、自由学園の建築群
A(亜紀): 先日、東久留米市にある自由学園を見学してきました。
私はこれまで池袋の「自由学園明日館」は何度か訪れたことがあったのですが、自由学園のメインキャンパスは初めてでした。docomomo japanに登録していたので、通常は見学できない建物の内部まで特別に案内してもらえたんですよ。
docomomo japanは近代建築の保存と記録を行う国際組織でして、2019年に自由学園南沢キャンパスの建築群を「日本におけるモダン・ムーブメントの建築」に選定(2023年に追加選定を行う)しました。
S(志水): ほー。建築好きとしては外せない場所ですね。
大正10年(1921年)に創立された自由学園は、2021年に創立100周年を迎えたんですよね。
池袋の明日館はフランク・ロイド・ライトが設計したことで有名ですが、現在の東久留米キャンパスはどうでしたか?
A: ライトの弟子で、明日館建設時にも助手を務めた遠藤新が設計した建物群が点在していて、とても見応えがありました。
特に女子部の校舎エリアは、2022年に東京都有形文化財に指定されたそうです。食堂や講堂、体操館などの建物だけでなく、それらをつなぐ回廊や芝生、中庭まで含めた景観全体が文化財になっているんですよ。

高等部食堂付近
さらに興味深いのは、遠藤新の息子の遠藤楽もライトに師事して、その後のキャンパスの図書館などの設計を手掛けているんです。親子二代にわたってライトの建築思想が継承されているんですね。
S: 建築的な価値だけでなく、キャンパス全体の環境としての価値も評価されているんですね。
建物写真を見ていると、低く抑えられた屋根、水平ラインを強調と、ライトの特徴であるプレイリースタイルが継承されているように思いましたが、そのあたりはいかがでしたか?
A: そうなんです。横に広がる伸びやかなライン、前庭の豊かさもあって、その名前の通りプレイリースタイル(大草原:プレイリーに溶けこけ込むようなデザインという意味)だなあと思いました
特に女子部の校舎エリアは、中央に食堂があり、その左右に教室棟が配置され、さらに講堂や体操館も含めて、シンメトリーが美しくバランスの取れた配置になっていました。
S:遠藤新は学園新聞に寄稿した文章の中で、「体操場が前衛で、講堂は大本営で本陣に測行するといった陣立て」と表現していたそうです。建築全体が一つの調和した世界を作り出しているんです。
自由学園は自然環境も豊かだと聞いていますが、その点はいかがでしたか?

高等部教室棟
A: 約10万平方メートルのキャンパスには約5000本もの樹木があって、小川も流れています。東京都内とは思えないほど豊かな自然に囲まれていて、生徒たちがその中で学ぶ環境が整っているんです。建物と自然の調和が素晴らしかったです。
S: 木造の校舎と緑豊かな環境、そのバランスがライトや遠藤新の建築思想にも通じるものがありますね。
自由学園の創立者である羽仁もと子・吉一夫妻が目指した教育理念と、建築環境が見事に一致している場所なんでしょうね。
自由学園と学園町の一体感
A: 私が特に印象的だったのは、学園だけでなく、周辺の「学園町」という住宅地も含めた一体感でした。
自由学園の敷地の外に出ても、同じような雰囲気が続いているんです。
S: 「学園町」ですね。自由学園が開発した住宅地として知られていますよね。
亜紀: はい。1925年頃、自由学園が東久留米に移転する際に約10万坪の土地を購入し、そのうち3万坪を学園用地として、残りを住宅地として分譲したそうです。
自由学園の教育理念に共感する人々が集まって住み始め、一つのコミュニティを形成していったんですよ。
志水: 学校が住宅地を開発するというのは、当時の成城学園や玉川学園なども同様の取り組みをしていましたね。
でも自由学園の場合は特に「教育思想と生活思想が密着した」住宅地と言われているそうです。
亜紀: そうなんです。
創立から約100年経った今でも、その精神は受け継がれていて、住民が街の魅力や景観を守り続けているんですよ。当時の武蔵野の森の木々を残して建てられた家は、ライトや遠藤新の建築スタイルを意識したデザインが多く、芸術や自然を大切にする気風が街全体に根付いています。
その街の雰囲気を愛して移住してくる人もいるようです。
志水: 土地の分割や新築も増えてきているとは思いますが、学園の思想が街の中に生き続けているということですね。
建築だけでなく、コミュニティとしての持続可能性も重要な視点です。
亜紀: 登壇されていた学園町の町内会長さんも4代前から住み始め、ご本人とお子様たちが自由学園出身だそうです。
海外に長くいらした方のようで、風通しのいい街を作りたいと話されていました。
お互いに尊重し合いながらも、押し付けではなく、住民主体で街を守り育てていきたいという思いが感じられました。
S: そういう方々が住んでいることが、100年近く持続している秘訣かもしれませんね。
教育機関としての学園と、生活の場としての住宅地が、適度な距離感を保ちながら共生している。
A: そうですね。
建築を通して教育理念が表現され、その思想が街並みを形成し、さらにそこに住む人々の生活文化となって受け継がれていく。
建築が、人々の生き方や価値観を形づくる力を持っていることを改めて実感しました。また、興味深かったのは、建物や設備が古くなり不便になった部分についても、生徒たちと学園側が、都を巻き込みながら、協力して改装や修復を行っているという点です。
文化財として保存するだけでなく、現役の校舎として使い続けながら大切に守っている姿勢が印象的でした。
S: 私たちが住宅を設計する時も、その家だけでなく、街との調和や、そこでの暮らし方まで含めて考える必要がありますね。
自由学園と学園町の関係は、建築が地域コミュニティに与える影響を考える上で、とても良い事例です。
A: はい。
住居は点ではなく、面として捉える。
そして時間の経過とともに変化しながらも、核となる価値観が持続していく。
自由学園を訪れて、改めて建築の社会的な役割について考えさせられました。
S: 亜紀さんのお話を聞いていると、私も一度訪れてみたくなりました。
次回は一緒に行きましょうか。建築だけでなく、街全体のデザインという視点で見学するのも面白そうですね。
A: ぜひ!季節によって表情も変わると思うので、また違った時期に訪れることができたら良いですね。

自由学園初等部、後頭部から比べるとこじんまりしたつくりです